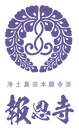
その他の記事
僧侶・得度について知りたい方へ
浄土真宗では僧侶になることを「得度(とくど)する」と言います。
報恩寺では平成27年以降、たまたまのご縁が相次いで、寺族(お寺の生まれまたは家族)以外から5名の僧侶が誕生しました。4名はその後教師資格(住職となることができる)も取得し、1名はちょうどタイミングや条件が整って、同じ組内寺院の後継住職となりました。
僧侶になるということは、基本的に仏事法要を営んだり、布教活動をすることです。また仏法に基づいて、常に自身の信仰や人生を問い、社会の中でどんな役割を担うのかを模索することでもあります。上述の衆徒や住職らは、他に自身の仕事や活動をしながら、お勤め・研鑽・地域活動・宗門の役職などに励んでいます。
ここ数十年、現代社会は目まぐるしく移り変わっていますが、仏教や信仰世界に関心を持つ方の割合は一定数さほど大きな変化はなく(NHK定点調査)、一方では社会的な規範に納まりきれなかったり、将来見通しに不安を感じる方々は多くなっているようです。
その中で、男女問わず在家一般の方々が仏門を目指すケースも増えており、このページはそういった方々へ、浄土真宗本願寺派としての情報と住職所見を記しました。
得度・僧侶についてご興味がおありの方は、まず下記の「補足」及び「Q&A」をご参考にしてください(住職の主観も入ってます)。基礎的なことはある程度ネット上でも調べられますが、実家の菩提寺や近隣の寺院、僧侶の方とお会いして具体的なお話をお聞きするほうが大事です(宗派教団によって相当異なります)。
その上で、もし具体的にご確認ご相談されたいことがあれば、お尋ねになりたいことに加え、下記1〜6
1ご住所(町村レベル)
2家族構成
3ご実家の宗派
4職歴
5仏教または真宗のどのような点に惹かれたのかきっかけなど
6僧侶としてどんな仕事をイメージされているか
について合わせてお聞かせください(4-6はおよそで結構です)。お問合せフォームよりご連絡いただきましたら、住職がメール相談に応じます。
*実際に得度を目指されたい方は、お住まい近くのご住職やご寺院とのご縁をまず先にお探しいただくことをお勧めします。
*現在、当寺院においては、原則住職後継者となれる方を前提として、新たな衆徒のご相談を受け付けております。具体的な、寺中(上寺・下寺)というやや特殊な関係であることや、実際の法務については個別にご説明いたします。(令和5年1月)
*なお、得度に関連する以外のお悩みご相談についても承っています。お気軽にどうぞ。
【いくつか補足〜お問い合わせの前に】
1)お問い合わせいただく前に、まず当寺院は宗門(浄土真宗本願寺派)全体ではひとつの末寺に過ぎず、特別な養成プログラムや人的体制を備えているわけではありません。結果的に現在、後継住職として若々しい活動を展開しているY氏をきっかけに、口コミで得度とその後の勉強をお世話させていただいた経験をもとに、在家一般の方にとっては未知の世界であろう僧侶の道について情報提供を行い、メールやお電話にてアドバイスなりご教示をさせていただいています。
当然ながら、志望者皆それぞれに個別の動機や事情を抱えておられ、指導させていただく側としても大変勉強になり(自分のような中途半端な坊主で良かったのかどうかはわかりませんが)、そのようなご縁をいただけるのは、寺を預かる者として有り難いことです。念仏者・僧侶を育てるというのは、住職という立場であれば本来特別なことではないものの、特に真宗各派においては世襲寺院が多く、社会状況が大きく変化している現在、一般社会人として揉まれた経験やスキルも、仏教界全体にとって大事だと考えます。
2)ただし、仏教の勉強をしたい、自身の生き方において飛躍を図りたい、信仰を深め確立したい、俗世間を離れて生きたいという段階に留まるのであれば(決して悪いことではありませんが)、労力をかけて僧侶となる必要はありません。宗門関係学校や養成専門校に入学したり通信教育課程を受けるとか、近隣の寺院で仏事や法話会に通うなど、学び探求する方策は種々あります。
僧侶になることは人生の一大転換です。そこで、自分自身に何を求めたいのか、生活設計や仕事の兼ね合いはどうするのか、どういった方面の活動に関わりたいのかなどの将来ビジョンを、ある程度明確にお考えください。そのためにも、仏教や僧侶という仕事について、あらかじめ実際のお寺さんに触れて実態を知っておくことがまず大切です。伝統教団はセミクローズな組織ですから、世間から見ればかなりズレた感覚、保守的・格式的な面も往々にしてあります。さらに、僧侶や各寺院においても、その来歴や性格、価値観、運営態度などはいろいろです。
もちろん、はじめから志を確立して臨む方は少なく、(寺族であっても)多くは実務や精進を重ねる経験の中で、生涯かけて探求するものでしょう。
3)上記の点を理解した上、どうしても止むに止まれぬ事情や発心をもとに得度に臨まれ、僧籍を得たとしてそこからが本当のスタートです。所属寺の法務に携わりつつ現場の仕事を覚えないと役に立ちません。その上でどこかの寺院の法務員(役僧)となったり、住職資格をとって入寺したりなど次のステップはご縁次第ですが、普段は他の仕事をしながら兼業の方も多いです(特に田舎では)。
しかしいったん宗教者となれば、自らを律し、儀礼を執行し、法を説くという、世俗から一線を画す人間とみられることになります。世間には(宗派問わず)多種多様な寺院、宗教者がおられますが、僧侶は資格・生業というより、覚者の教えをもとに生と死、聖と俗の間を行き来するような、ある種緊張感のある生き方であることをご承知ください。
【Q&A〜具体的なあれこれと私見】
1誰でも僧侶になることができるのですか?
本宗派に関して言えば、手続き上は男女問わず誰でも僧籍を得ることは可能です。ただし、僧侶として読経する上では普通程度の音感と声量は必要ですし、最低限の専門用語や作法、教義や歴史などに関しては覚えなければなりません。また、正座が多いので膝や脚に大きな不具合がないことが前提となります。真宗教団では他宗派と比較して易しいと思いますが、現実的には中年以上の方は体力面、暗記面などでの苦労を覚悟すべきでしょう。
また、外部と接触は一切できない二週間の習礼(詳細別途記載)では、男性では剃髪、女性は髪を束ねて耳を出すなど少々厳格な規則を守らねばなりません。
なお、得度の手続きや、得度に至るプロセス、得度可能年齢や一連の費用については、各宗派教団によって異なります。ちなみに、本願寺派以外(大谷派、高田派など)では一二日の簡単な儀礼にて僧籍を得ることはできます。しかしその後、所属寺に通って住職流の手解きを受けたり、別途専門学校や本山に通って実務を身につけられていると聞きますので、各宗派にてお調べください。
2僧侶として心構え、適性みたいなものはありますか?
僧侶を目指す動機や資質、家庭事情や職歴などの人生経験はそれぞれであり、はじめから信仰心が篤いとか救いを希求する人間が僧侶にふさわしいわけでもありません。
お問合せをいただく一般の方の中には、仏教に勉強熱心な方のほか、ある種過酷な状況において生きづらさを抱えたり、人生や自分自身に行き詰まりを感じたり、その中でもそういった経験を糧にして前に進もうとか、あるいは仏法や僧侶にあこがれが高じたりなど、少なくとも何か自分の生き直しを図ろうという発心が強いようです。
ただ、僧侶としての仕事(法務)の中では、向き不向きの問題はないとは言えません。
まずは仏教・宗教について虚心で学び、己の抱える闇や業を見つめ、人の話に傾聴して相手の悩みや苦しみに向き合って、本当の救いとはどういうことかにフォーカスする。利他的精神を忘れず、命の尊厳を損なうような社会の歪みの解消に力を注ぐ姿勢も求められるでしょう。
勿論これら一朝一夕に培われるものでもないし、達成できるかどうかもわからず、自己満足かもしれません。しかし自分の生涯をかけて問い続けていく覚悟が必要と思います。
読経や作法、法話、ご門徒さんへの対応、事務全般などに関しては、得手不得手もありますが不断の努力や勉強、法務を通じて少しずつ習得すればよいでしょう。
本願寺派の僧侶規定には、剃髪や菜食、作務衣着用の義務などはありません。その分、法衣を着用していなくても、宗教者としての自覚を厳しく保つことが求められます。他の仕事と兼業していても、普段の言葉使い、所作、食事、金銭感覚など、僧侶として恥ずかしくないよう心がけは必要です。
3どのようにしてお寺さんについて習うのですか?
得度にあたっては、いずれかのお寺を訪ねて所属し(衆徒)、住職に指導や手続きなどお世話いただく必要があります。どのようにして所属寺ご住職を探すか、ここが一般の方にとって最も難しいところです。
まず、家の菩提寺が本願寺派であればそちらにご相談されるのがスジです。
得度後も所属寺の法務に出向いて経験を積んだり、所属寺の報恩講や永代経法要、盆、正月などの仏事法要にも衆徒という立場で準備や勤行に出仕するのが普通です(寺院によって関わり方はさまざまです)。よって、所属寺はお住いから通える範囲が(多少遠方でも)ベターです。
ひとくちに寺院や僧侶といっても、田舎と都会、専業か兼業、寺族か在家出身か、あるいは個人の人生経験や寺の歴史などによっても千差万別です。後継者を前提にしない方の得度を引き受けることに抵抗を持たれたり、在家の方を衆徒に迎えることに余裕のない寺院の方も珍しくはありません。末寺の情報を持っている各地の教務所・別院でいきなり尋ねても、職員の方から簡単に紹介をいただけることはほぼ期待できないと思います。
まず、お住まいの地域の教務所・別院、各寺院で開かれる仏事法要・各種行事に参拝したり、公開講座、勉強会などに参加して、ご講師や住職らをご自分の眼で確かめてみる。直接ご挨拶をしてご相談されたり、どなたかご紹介をお願いするなど、時間がかかりますが、地道に足を運ぶなり人伝てを頼むなどしなくてはならないでしょう。
4本願寺派の得度では、どんな勉強や修行がどのくらい必要ですか?
・学習内容
最小限の読経として「正信念仏偈」「御文章」「讃仏偈」「重誓偈」「葬場勤行」「仏説阿弥陀経」などを練習します。領解文。生活信条、正信偈の一部などは暗唱が求められます。また、内陣出勤を含む基本的な作法、仏具などの荘厳、衣体の被着法も実習します。
知識的には仏教全般の学習、真宗の基本的教義、歴史などを学び、仏具や作法も含めて漢字で書けるよう覚えねばなりません。
これらについては所属寺院の住職などについて勉強しますが、ご自身で自学自習し、勤行も音源など利用して何度も反復実習が必要です。頻度や進行具合、各地での講習会や習礼の時期にもよりますが、短くても半年以上〜1年程度準備をかけることが望ましいでしょう。
なお、真宗教団では、仏教一般で言う戒律や行はないため、「修行」という表現は用いないのが普通です。そのぶんかえって、僧籍を得てからも自らの精進について、常に律し続けることが必要です。
・得度講習会と得度考査
勉強期間の中で、2日間の得度講習会、1日の得度考査(試験)を受けなければなりません。得度講習会は各教区教務所で年1~2回(福井教区では年一回8月頃開催)、京都の宗務所・西山別院ではほぼ毎月開催されます。得度講習会では先述した内容を一通り習い、終わりに筆記テストがあります。
原則、講習会とセットで(三日目)得度考査が行われます。考査では筆記試験と実技試験(正信念仏偈の実習)、そして面接があります。事前によく勉強し、講習会と考査を余裕を持ってクリアして、その後の得度習礼で遅れをとらぬように臨みましょう。これらの受講には装束や冥加金も必要になります。
・得度習礼
講習会と考査を通過すれば、京都の西山別院で行われる10泊11日の得度習礼に申し込みです。年に7回ほど開催され、男性は剃髪して入所します。
習礼では全国から一般の方や寺族の方々が集まり、通常50名ほどで集団生活をします。期間中は携帯電話はもちろん、一切外界との接触が禁止され、缶詰め状態となります。早朝から夜遅くまで、食事時間もそこそこに分単位のカリキュラムをこなし、わずかな空き時間も復習や予習に追われます。
生活と実習は班単位となり、ミスをすると連帯責任でやり直しです。座学と食事以外は正座での実習となります。体調を崩して途中退所する方もたまにいるようです。またグループ研究で、僧侶としての自覚を深めていく話し合い法座が持たれます。
理解度調査なるテストや、期間中の諸課題を全てクリアした上で、最終日に本山・西本願寺での得度式を経て、僧籍が許可されます。この際には法名が必要で、事前に所属寺住職とも相談の上、申請しておきます。
5それらに関わる経費はどのくらいかかりますか?
講習会や習礼の冥加金で約15万円、習礼費で12万、装束やカバン、書籍購入などで約20万ほど。また、所属寺院への勉強代が求められることもあります(事前にご確認)。
僧侶となってからでは、実際の法務として夏冬の装束、(得度では使わない)五条袈裟や勤行聖典なども揃える必要があります。また、宗派へ年間1万数千円の冥加金も含め、それらの経済的一部は所属寺院が負担することもあるかもしれません。
6得度後はどんな生活、どんな仕事に就くのが望ましいのでしょう?
浄土真宗を含め日本は在家仏教であり、社会と隔絶した出家生活を送ることは極めて少なく、普通の会社勤めや教員公務員の僧侶も珍しくありません。基本的に一般の方々と同じような生活をしながら、僧侶としての務めをこなします。現実には各位のご家庭やお仕事の事情次第で様々ですが、以下に参考としていくつか挙げておきます。
・日々の生活
僧侶となった以上、ご自分のお仏壇(なければ携帯用のご本尊でも勿論OK)で毎朝勤行し、所属寺で引き続き勉強、法務に同行するなどして、現場に対応できるよう引き続きスキルを高めましょう。また、教務所や近隣のお寺の法座など、お聴聞の機会をできるだけ作って仏法の学びに精進しましょう。世間での仕事や人間関係、社会の出来事の中においては、世俗的な価値観でなく仏教・真宗の教えからの視点で見直していくトレーニングも必要で、そのためには書籍やネットのほか、周囲に先輩や仲間がいることも大事です。
・実践の現場
所属寺院やご門徒宅での種々の仏事を経験し、習熟していくことが必要です。最低限、所属寺院の仏事(報恩講、永代経など)には出仕し、急な葬儀などは仕事の都合がつけば出仕しましょう。
ご門徒とのおつきあいや、一般の方との(僧侶としての)交流においては、相手の心情や疑問、家庭内の事情などを教えてもらうつもりで、信頼関係を築きながら仏法を伝えていくこと。失敗や耳の痛いことを指摘してもらえる関係こそが財産です。
教務所や本山などの法要や研修会・学習会に参加して、教団としての活動現場も知り、意に叶う先生方や人脈を広げることも大事です。
また宗教者として「命を大切にする」という視点での、自死、貧困格差、差別、教育、医療、福祉、環境、戦争や原発、災害支援、脱カルト支援などさまざまな社会問題に取り組んでいる宗教者や団体もあります。例えば「ビハーラ活動」(本願寺派)とか「臨床宗教師」など、布教を全面にせず傾聴活動によって、患者や当事者、ご遺族によりそうケアーのニーズは高まっています。
地域の活性化なども寺院のポテンシャルが試される領域で、過疎化・高齢化という社会の変化に対応し、ご門徒や地域の方々と一緒にさまざまな企画イベントでお寺という拠点を運営発展させ、地域に貢献していくことも大切な役割です。
・お寺を継ぐ(入寺する)
後継に課題のある寺院は少なくなく(当寺院もそうですが)、さまざまなご縁によってお寺の住職を継ぐ前提として、教師資格を取得していなければなりません。本山にて二週間ほどの講習と八科目の試験(法話実習含む、年三回あり)を受け、全科目合格したらやはり西山別院で11日間の教師教修を経ることが課せられます(前期後期と分割も可能)。事前に10分程度の法話原稿を提出、ほぼ暗記が求められます。これら勉強期間も一年程度、寺院での内陣出仕や法話(布教)など、より実践的スキルと仏法理解の学習が必要です。
なお、住職は世襲とは限りませんし(在家の婿の方が継ぐ場合もあり)、法務の忙しさは寺院の活動、門徒数や地域によってもかなり違います。兼業しながら苦労して護持している寺院も少なくありません。何れにしても住職となれば住むのが仕事。早朝は月参り、土日は法事、葬儀は急に入りますし、365日営業です。
・専門性を高める
布教活動の専門家(布教師)を目指したり、お勤めの専門養成課程(勤式指導所)に進むこともできます(それぞれ本山にて半年~1年間の研修生活)。年齢制限や教師資格など条件もありますが、教団関係諸機関の職員に応募することも選択肢として考えられます。
地域や寺院の規模によっても異なりますが、数名の僧侶を法務員(役僧)として雇用している大寺院もあります(その場合所属寺院を変わることも可能です)。
・役僧(やくそう)になる
所属寺院または近隣寺院での仏事や葬儀をお手伝いをする専門僧侶を役僧といいます(上記の法務員を指すこともあり)。役僧という立場を生業としている方も地域ごとにおられますが、収入面で安定するためには、一定程度多くの寺院で法務または裏方作業をこなせるよう、仏事全般に習熟した経験が必要です。ちなみに真宗寺院においては、報恩講が務まる秋冬の繁忙期に役僧の出番も多くなります。
7一般社会の中で、僧侶として今どういった課題がありますか?
問題意識の持ち方について、これも寺院や僧侶が置かれた立場や経緯によって色々でしょうし、属している宗派教団の構造的な問題、負の側面も存在します。下記、いくつか書き出してみると、
・お坊さんって頭が高い!?
若院時代から門信徒からちやほやされ、営業努力も不要で、自らの救いを真剣に追求した経験もなく、親戚や近隣寺院の狭い付き合いに留まり、同じ宗派や教団組織の風土に染まり、異論や他派・他宗教に耳を貸さず自らの正しさを押し付け、伝統的格式には敏感だが下の立場の者には見下し差別する..。といった闇から抜けられない状態を、ほぼ全員の僧侶は経験しているはず。
寺の敷居は低過ぎてもどうかと思うが、謙虚さを忘れるほうがもっと困る。
・坊主丸儲けなの!?
寺院(宗教法人)は税金がかからない、というのは宗教活動においてのこと。寺院の運営は水道光熱費、車、通信機器、修理営繕費、学費や接待費も含まれて、その按分次第では一般事業者より恵まれてもいる。ただし、門信徒数二桁ではお布施・宗教活動ではとうてい生活できず、兼業して収入を維持運営に充てるか、多額の寄付金や維持費を募るしかない寺院のほうが多く、大寺院であっても維持管理の負担は大きい。
いずれにしてもご懇志・金銭感覚は世間と乖離してしまいがち、贅沢はいかんな。
・どうする、寺離れに簡素化!?
戦後世代とそれ以前では信仰態度や寺院と付き合い方がかなり違うようだ。地域共同体や寺院が果たした機能も衰弱し、少子化高齢化過疎化が進む中でコロナ禍が葬儀・仏事の簡略化にも拍車をかけた。といっても、人々の信仰心は例えば東日本大震災の際には高まったり、アニメにも宗教的要素がちりばめられたり、お墓参りだけは盛況する(本堂にはお参りされないが)。
檀家制度にこだわらず、若者や地域住民らが多く集う仕掛けを打ち出している寺院や、地道な活動・ユニークな試みをしている僧侶も、探せば各地におられる。今後ますます生活の中の信仰は廃れていくとしても、普遍的な拠り所を求める気持ちはなくならないだろう。
安易な策は注意として、急激な変化についていくべく模索は続く..。
・そもそも宗教ってな〜んかアヤシくない!?
少し前のスピリチュアルブームに、オウム事件やらカルトとか、宗教自体にイメージ悪っ!としたら誤解です。というかお坊さん個々人や業界全体の怠慢。というか教育やメディアにも責任ある。政教分離とか信教の自由とか言って宗教を考えることをタブー化してしまい、学校でも社会でも宗教リテラシーが育まれなかった。諸外国では信仰を持たないとそれこそテロリストかと怪しまれてしまう。
現代生活ではまるで科学技術が宗教のように振る舞い、TVや瞬時に駆け巡る情報に洗脳され、倫理道徳では人間の置かれた不条理は解決できない。確かに生死両面を扱う宗教は、狂うというアブナイ面抜きには成り立たないし、だからこそ芸術・文化・芸能・習俗面に豊かな奥深さをもたらしてきた。仏法は実は最先端の量子論・生物学研究にも親和性がある。
仏教経典は漢訳ばかりで意味不明に聞こえるが、人間社会への深い洞察に満ちてるよ。
・戦争は宗教が原因なのでは!?
原因は人の欲の暴走だ。国家という目に見えない存在がそれに火をつける。刀からミサイルへと武器の進歩もすさまじい。歴史を紐解けば、諸民族の統治機構と宗教勢力との関係は多岐に渡り、密接不可分である(一神教ほどではないが仏教国でも争いを助長した)。
国同士だろうが家庭内だろうが、古来から人間同士のいがみあいは絶えないからこそ、どの宗教でも平和や思いやりを語ってきた。非暴力によって争いを解決した偉人や、自らの身命を投げ打って他者を助けた名も無き人々もあふれているに違いない。
縁起に従って種が果実となる。少なくとも自分の行為が人の罪を作らせないようにね。
以上、私見混じりですがひとつのご参考にしてください。(文責 住職 林 暁)